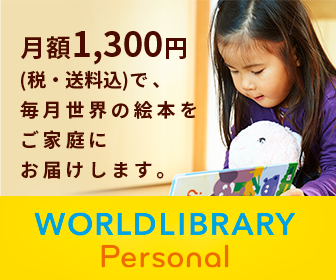先日ブログで、前田裕二さんの本「メモの魔力」で具体から本質的な抽象を抽出して日常に役立てたり、仕事で役立てたりしているという記事を書きました。
抽象というキーワードが心に残りました。
子どもっていつから具体と抽象を行き来できるのだろう。小学校4年生になると抽象化の問題が増えてくるので、成績の伸び悩む子どもも出てきます。
調べてみると、副産物でこんな本を見つけました。
国語が得意科目になる「お絵かきトレーニング」坂本聡著
坂本さんは考学舎という塾の代表の方です。
この本では、
具体と抽象とは違いますが、抽象化の前に、まずは言語化するトレーニング、人にわかりやすく説明できる力が養えます。
考学舎では全教科の基本の国語が得意になるように体形立てて学習をしているところです。
日常の中でどんなことを意識したら国語が得意になるか、また、その力は将来の仕事や生きていく力とも重なります。
バイリンガル、トリリンガルという言葉を聞くこの頃ですが、何か一つ母国語を深めることで深い思考を深めることができます。
日本語を深めて使えるようにしていくことは大切です。
さて、どんな子が国語が得意になるか本から紹介をします。
わからないと言える子が国語ができる。
わからないと言える子供が国語ができるそうです。
わからないと言うのは、根底にわかろうとする心があるそうす。
わからないと子供から疑問がでた時に親は、わからないに付き合ってあげる親が良く、
何がわからないのか?
なんだろうね。
一緒に調べようか。
とそこから考える習慣を持つのが望ましいとのこと。
国語に限らず学ぶことの共通は、わかる。わからない。をしっかり認識することが正しい理解につながります。
なんだろう?と思った時にすぐに答えが用意される習慣を持たない方が良いとのことです。

多くの子供が悩むこと
知識を問う問題が解けても知識を使う問題が解けない。計算はできるけど文章題が出来ない。
知っているはずの知識を組み合わせることができない。
多くの子供はここで悩みます。
評価が○✖️で決まる。学校の授業も要因の一つです。
わからないところをしっかりおさえ、
正しい理解を積み重ねることで応用ができるようになってくるとのこと。
わかっているかの確認、、言い換えてみる
わかっているかどうか?言い換えてみることで確認ができるとのこと。
言い換えの習慣を体得していくことが全ての科目において応用のきく生徒の特徴だそうです。
例えば、本を読みながらその情景を思い浮かべてみる。自分なりに何かを思い浮かべた時に言語化するくせがついていることが重要だそうです。
国語力をつける大切な3つのこと
考学舎の国語力をつけるヒントが載っていました。参考にしてみましょう。
理解する力
外からの情報を受け取った時の感覚を、言葉におきかえ主観的な感情にあ終わらずに
客観的に自分なりに噛み砕いて自分の中に取り込む。
普段の出来事を言葉にするということですね。
例えば、
お友達と朝会った時に、おはようと言ったのに何も言ってくれなかった。
ということを言葉に出来たら、
今度は自分の「せっかっく元気に挨拶をしたのに、挨拶をしてくれないなんて寂しいな。」という自分の気持ちが出てきます。
その後に相手目線になってみる。
そういえば、元気がなかったな。お母さんと朝、喧嘩してきたのかな?宿題を忘れたのを思い出したのかな?等 客観的に考えてみるということでしょう。
言語化って難しいです。低学年では自分の思ったことを言葉に出来ない子もいるので、お母さんが変わって言葉を表してあげてもいいと思います。
自分では、なかなか出来ない作業なので、親子の会話が思考を深めます。
自分の考えと比較し決定する力
自分の今まで経験したことの中から、比べてみたり、それでいいのか考えてみる。
賛成の時には、賛成の理由を考えてみる。とのことです。
感想文や作文はこの要素を織り込みながら作り上げていきます。
しかし、学校では一人、一人にあった指導はできないので、
まずは、お家で絵日記をかき、お母さんと日本語の書き言葉をまとめていくことから始めて、
出来事に対して、自分の意見や感想をまとめていくといいですね。
こちらの塾では、
資料の整理等の学習をしているそうです。
中間一貫校のテストで資料の分析がよく出るので、似たような感じかな?と想像します。
これは、小学校の高学年くらいのレベルだと思います。
適切に表現する力
自分の考えを、その時、その状況に合わせて説明、言語化できる力を育てる。
以上。この3つのステップを使って国語力に繋げていくようです。
語彙力をつける。物語文の書き取り。新聞記事の要約。とうで積み上げていくそうです。
実際の本の内容を見てみましょう。
本書では、絵を文章化する。
文章を絵にするということから国語の基礎を養っていきます。
本の中を見てみましょう。

どうですか?これは子供が楽しくできそうですね。💓
進めていく保護者へのアドバイスも書いてあります。ありがたいですね。ここからレベルがアップしていきます。
これは一番最初に取り組む問題なので書き込み形式になっていますが、
ポイントとしては、全体を説明してから、この場合上から下へ移るという順番がいいよというアドバイスがありました。
脳はわからないと拒否をしますので、まずは全体が想像できる、そして詳細を説明するのが
鉄則です。新聞等がそうですね。
次は、絵から文章へです。

文章からイメージへ、イメージカラ文章へと行き来できることが
重要のようです。
本の中にも書いてあったのですが、勉強のできる子供は、
物語でも読んでいるときに、その情景が浮かぶようです。
ここでは勉強ができると書いましたが、
社会に出ても、理解力がはやい方は、同じように、イメージがすぐにできるのだと思います。
まずは、日本語の正しい、言語化、イメージ化をしてみましょう。
この本では、わからないところが、わかるようになると言っています。
チャレンジしてみるといいですね。
この本は、小学3年生以上程度だそうです。
2年生の教科書に掲載されている程度の文章を、大人と一緒に読むことができる。(音読)
100じ程度の分をかきとることができる。
文章には、主語と、述語があることを知っている。状態であれば取り組めますとのことでした。
日本語の文章を取り入れるもの
音読や書き取りでおすすめのテキストが載っていました。
音読は私もお勧めします。まずは体の中に頭で考えることなく体得していくことが子供の頃は重要ではないかと思います。
まどみちお詩
- たまねぎ
- きりん
- アリくん
- こねこねこのこ
- けしごむ
- つけもののおもし
- カバはこわいよ
谷川俊太郎 詩
- かかし
- すりむきのうた
始めて取り掛かるもは無理のない量ですね。
コツコツと母国語の深い思考を作っていきましょう。